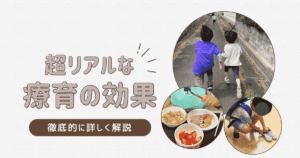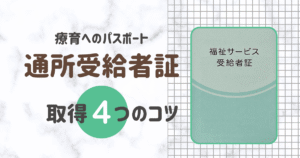- 変わったしぐさや行動が見られる
- 味やにおい・音に敏感すぎる
- 特定のものへのこだわりがある
「うちの子、他の子と違う気がする…」
同じ年のお友達との差が少しずつ開きはじめて、”もしかしたら…”と不安を感じたことはありませんか?
私が息子に対して感じていた違和感が、確信へと変わりはじめたのが2歳代でした。
一生懸命大切に育てているつもりなのに、なぜか他の子のようにうまくいかない。
こだわりの爆発期を迎えて、一気に「育てにくさ」を感じるようになり、一日一日をやり過ごすので精一杯。一体何をどうしたら息子の成長のためになるのか…苦しい思いを抱えて各所に相談しはじめた頃でした。
しかし、自閉スペクトラム症特有のこだわりが強くても知能が正常範囲だったため、支援の対象者としてはグレーゾーン的な存在だった息子。
相談に出掛けた健診や自治体の発達相談センターでは「様子見」と言われ続けたのです。
この記事では、自閉スペクトラム症と診断され支援に繋がるまでの道のりを共有しております。
コチラの続きになります↓
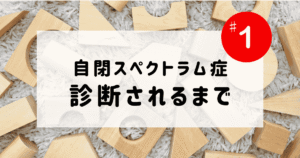
 羊ママ
羊ママわが子の発達に違和感を感じている親御さんの参考になれば幸いです。
2歳:こだわりの爆発期がやってきた


自閉スペクトラム症の二大特性は、「こだわり」と「コミュニケーション障害」と定義されていますが、まさにこれらの特性がはっきりと出始めたのが2歳代。
ただし、今振り返れば「特性」と言えることでも、この時期の子どもは発達の個人差が大きく、個性なのか障害なのか当時は判断しずらい状況でした。
それゆえに、相談機関先で「検査」を希望してみても、「検査はもう少し大きくなってから」「もう2~3か月は様子見でいい」等の返答ばかり。
今、苦しくて困っているのに、あと2~3か月もこのままの状態で待つの!?
月齢並みの発達課題がクリアでき、知能に遅れがないと判断された息子は、困りごとを抱えていても過小評価されてしまい、ギリギリ「普通」のカテゴリーへ押し込められていました。
母としても、この子は他の子とは”何か違う”とはっきりと気付いたけれど、支援に繋がることができなかった苦しい時期でした。
2歳0か月:トミカを一列に並べ横から観察
1歳から目立ち始めた感覚過敏に加え、道順や序列へのこだわりが激しくなってきた息子。
トミカを一台ずつ並べ横に寝そべりながら転がして、タイヤが回る動きを永遠に見つめている息子の姿に、「こ…これは…かの有名な特性スタイルなのでは」と検索魔になったのが2歳なりたての頃でした。
健常児にも見られる行動ではありますが、同じ年齢の子どもは車を並べるだけでなく、擬人化したり見聞きした物語を再現したり、遊びに広がりが出てくる時期です。
車を使って戦いごっこをしている親子やお友達同士の楽しそうな姿に「もうこんな遊び方ができるの!」と衝撃を受けた私。聞けば「自然に遊びが発展していった感じで~」と言うではありませんか!
「もしかしたらうちの息子もできるかもしれない」と、ワクワクとした気持ちで遊びに誘ってはみました。
しかし、「スン…」とした表情で反応なし。こんな感じだよ?楽しいよ?と私が遊んではしゃいでみせても「…」と微動だにしませんでした(涙)
それよりも、部屋の端から端までトミカを並べ、順番にタイヤの動きを念入りに見つめることに没入している息子。
自閉症の特徴的な行動の一つであることに動揺していた私は、その一心不乱な姿に異様さしか感じてあげることができていませんでしたが。
今思うと感覚過敏ゆえに混沌とした生きづらい世界の中で、唯一心和む時間がこの「パターン化された秩序ある光景」だったのかもしれません。
ちなみに、同じ光景を見た夫は、



おお!ここに職人がおるで!
↑ホクホク顔で褒めちぎっていました…
「何や!うちはトミカの整備工場になったんか?すごいな~全部並べたんやな!」と、同じものを前にしていても、こうも捉え方が違うのかと、無知ゆえのポジティブさに唖然といたしました。
見通しが見えてきた今ならば、「みんな同じに遊べなくてもいい。息子は息子の成長がある!」と胸を張って言えますが、「自閉症だったら…」と心配していた私にとっては、夫の能天気さに苛立ちを感じてしまっていました。



自閉症と診断された時よりも、この時の方が不安が大きかったです。
2歳3か月:公園で遊べない
公園には毎日のように行っていましたが、遊具では遊べませんでした。
1歳から対象の小さな遊具にも恐怖感があり、少しの段差を昇ってみては「怖い~」と涙目。特に滑り台には強い拒否感があり、普通に滑り下りることができたのは5歳をすぎてからでした。
ブランコにはニコニコ乗ってくれるものの、何故か「慣性の法則」に逆らった力をかけて動きを止め、”ぶーらんぶーらん”という動きではなく、僅かな揺れを静かに堪能している息子。
他人から見るとブランコにただ乗っかっているだけの不思議な光景だったようで、「遊ばないなら早く代わってよ~」と急かされることも多くありました。
また、砂場は最も悲惨な現場でした。
砂のサラサラ具合やキラキラ光る石の粒が息子のお気に入りで、唐突に自分の頭よりも上に砂を持ち上げてばら撒き、太陽に砂が透ける光景にうっとりと恍惚感を浮かべているのです。
一人でやるのならいいのですが、一緒に遊んでいるお友達の頭や顔にもかかってしまうものですから…さあ大変。
慌てて息子の行動を止めさせ捕獲。混乱して泣き叫ぶ息子を抱きかかえながら、被害に遭ったお子さんや保護者の方に謝罪する私。
相手の方々は「何か」を察知して許して下さいましたが、何度言い聞かせても止めてくれない息子は、公共の場で明らかに「困った子ども」になっていたと思います。
この子は、やっぱり普通の子と違う…
自分の小さい頃、公園は幸せな場所でした。お友達と遊具で目一杯遊んでクタクタに疲れて”あ~楽しかった”と家に帰る。それが子どもの当たり前だと思っていました。
ですが、息子の場合、遊具でも遊べない、唯一興味のある砂場でも迷惑行為。公園でさえまともに遊べないのです。
「どうして他の子のように遊べないの?」
悲しみとも苛立ちともつかない感情で、すごく虚しさを感じていました。
さらに、場面切り替えが苦手で、公園からの帰り際にも激しい癇癪。
次の行動や場所に移るまでに何時間もかかってしまったり泣き叫んでしまったりすることが増え、近所の公園に行くことすら一大イベントになっていました。
もう公園に行くのはやめよう…
公園でまともに遊べてない上に、帰り道がこれまた重労働。他の子と比べてガッカリしたり、誰かに迷惑をかけてしまったりするくらいなら、もう公園に行くのはやめようと心が折れてしまってしました。



人気の公園を避けて、人気のない遠くの小さな公園にたまに行く程度になりました
2歳4か月:くるくる回転
公園など広い場所にくるとやっていた行為、それは「その場でくるくる回転する」ことでした。
定型発達児がキャッキャッと楽しそうに回転する遊びとは一味違い、ゆっくりゆっくりスローモーションでひたすらに回転するのです。
さらに特徴的だったのは、その表情でした。
極限まで目を横上に寄せて顔は無表情。角度によっては白目を剥いているように見えるのです。
空が茜色に染まる穏やかな夕暮れ時にふとした瞬間に目にする、白目でスロー回転しているわが子。
エ…エクソシストーー!( ゚Д゚)
自閉症どころか悪魔にでも憑りつかれたの!?と、不気味すぎて心臓が縮み上がりました。
震えながら検索したところ、これは「常同運動」であり、ストレス緩和を目的とした感覚刺激の追及行動ということが判明。
特に自閉症の子どもにとって意味のある行動だと知り、「もしかして」から「やっぱり」と自閉症への疑いを強めたのでした。



初めて見た方は大抵ぎょっとしてたわ…



器用によう回って~フィギュアスケーターになったらいいんちゃう~?
かなり回転しているというのに、目が回らないのも不思議でした(←白目だから?)。
2歳5か月:常に手々ひらひら
これも「常同行動」のひとつ。
左利きの息子は、左手で鉛筆やスプーンを持ち、空いた方の右手は常にひらひらと動かしてしました。
6歳近くになった現在もこの特性は続いており、食事や歯磨きやドリルなど興味が薄いことをしなければならない時に、特に発動しているように思います。
ストレス緩和のためと目的が分かっているので、叱ったりして辞めさせることはありません。
ですが、お手々ひらひらのせいでコップが倒れて水浸しになったりと、食卓で見守る私はいつもハラハラ。
独特の動きで目立つので、周りから理解を得られずに学校で「いじめ」に繋がらないかは今も不安に思うところです。
2歳6か月:左手に特定のトミカを握る
そして、もう一つの困った「こだわり」も出現。
元々、就寝時に必ずトミカを左手に握り締めないと寝られないという儀式めいたこだわりがありましが、外出時にもトミカにまつわるこだわりが見られるようになりました。
その「こだわり」とは、道路で「はたらく車」を見かけると、同じ種類のトミカを左手に持ちたがり、それが叶わないと癇癪を起こすか座り込んで一歩も動けなくなる、というものでした。
例えば、都営バスを見かけたらトミカ版の都営バス、次にクロネコヤマトを見かけたらクロネコの宅配トラック…という具合で、歩いていれば次々に「はたらく車」が通りかかるものですから、これには本当に参りました。
最初は、ただのワガママだと思い「今は持っていないよ」「無理なものは無理だよ」と言い聞かせてみたことろ、今度は「おでかけいやだ」となってしまい、仕方なく息子の気持ちに寄り添うことにしました。
その結果、外出時のマザーズバッグには、常時20台ほどのトミカを持参。肩にずっしりと食い込み、重いことこの上なしです。
しかし、20台の精鋭部隊で対応できないこともあり、持参していない「はたらく車」が遠くから向かってくるのが見えた時には、「こっちに来ないでーーっ!」と心の中で必死に念じたものでした。
2歳6か月歯科検診での相談
次々と出現する、息子独自の「こだわり」や「しぐさ」に不安を感じていた私。
保健センターの2歳6か月歯科検診で、保健師さんにも相談しましたが、
- イヤイヤ期にはよくあること
- 発達に遅れはないので心配ない
- 今は子の要求に従ってあげるべき
- 個人差がある時期なので様子見
1歳半健診に引き続き、今回も「様子見」。
本当はもっと相談したかったのですが、コロナ禍の真っ只中で相談時間が限られていたのもありこの日は終了。
そして、違和感は感じているものの、親としても息子を「障害児」にしたいわけではありません。
こだわりはあっても息子は普通なのだから、面倒を見切れない自分が母親として未熟なだけなのだと受け止めて、支援に繋がるチャンスにはかすりもせず、会場を後にしたのでした。
2歳10か月:スタートラインにすらないトイトレ
一般的に、排泄機能が整いはじめる2歳前後の夏から開始するトイトレ。
3歳の入園までに完了させておきたいと思っているご家庭も多いのではないでしょうか。
しかし、息子の場合、1歳台から聴覚過敏でトイレの流水音に異常な恐怖心があり、トイレはもちろんトイレを連想させる”おまる”にも近寄くことさえできませんでした。
一度便器に座らせてみたら慣れるかもしれないと試したところ、便座から1㎜でも尻を浮かせようと必死に私にしがみついて泣き叫ぶ息子。



怯えたコアラのようでした
どうしてこんなにもトイレを怖がるのか、心の底からは理解してあげられませんでしたが、無理強いだけは良くないこと理解していました。
そのため、2歳間近に始めたかったトイトレを1年遅らせて大事に見守ってきましたし、漏らした時にきちんと不快感を感じられるよう布パンツに切り替えて、尿意・便意を感じたらトイレに行くという自然な流れも大切にしてきました。
勿論、育児書やネットのおすすめを実際に取り入れたりもしました↓
- トイレを楽しく装飾
- 抱っこして一緒に便座へ座る
- トイトレ関連の本&動画
- しまじろうのといれっしゃ
- 一日一回トイレに近づけたら褒める
- 大好きな車のご褒美シールを贈呈
しかし、どれも息子の助けになるサポートはなく、無駄に便通の良い息子のうんちパンツを日に何度も洗う日々…。
息子は頑なに自分からトイレに近づこうとしませんでした。
お友達が次々とトイトレ卒業をしていく中、トイトレのスタートラインにさえ立てていない状況に、「うちはうち、よそはよそ」と自分に言い聞かせていても、無意識に羨んで溜息をついてしまう私。



同級生と息子との間に広がりつつある「差」に焦りを感じていました
2歳11か月:偏食がさらに悪化
発達障害児には偏食が多いとの論文や統計がありますが、まさに我が子もその通り。
食事の時間は、本当に本当に地獄でした…。
こちらも1歳台から食感や味に対しての感覚過敏が出現しはじめ、一時は25品目程度は食べられていた食材が一気に10品目以下へ後退。
毎食「何なら食べられるの…」と疲労困憊。
小さく生まれた上に偏食で、息子の体重がなかなか増えないことに日々必死でした。
レシピ集を見て献立を研究するのはもちろん、親だって滅多に食べられないブランド牛や天然魚などを特別に買って素材にもこだわり、野菜をお星様や花型にくり抜いて楽しげにするなど、全方位に抜かりなく配慮するも…息子の胃袋を掴むことができず全敗。
「好きな物だけ食べさせればいい」というアドバイスもありましたが、幼少期の栄養不足がさらに発達障害を悪化させたらと考えるとそうも振り切れるわけもなく。



栄養か心の安寧か…毎日がせめぎ合いでした
“やっとの思いで4か月で0.5kg増やしたのに、ここで気を抜いたらまた元に戻ってしまう”と、鬼気迫る思いだったのです。
しかし、母親の願いとは裏腹に、美味しく食べてもらいたいと作った料理がぐじゃぐじゃにされただけが何度も続くと…
虚しい…悲しい…悔しい…腹立たしい!
あまりにも息子への通じなさに、腹立たしさで母であることを忘れる瞬間もありました。
感情に任せて料理ごと皿をゴミ箱へ叩きつけて、「こんなの思っていた育児じゃない!」「子どもなんていらない!」「私を一人に戻して!」と、わんわん泣いたことも…。



いつも疲れていて少しのことで心が決壊しそうでした
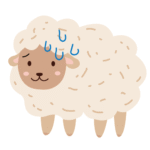
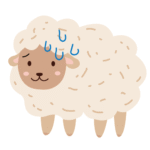
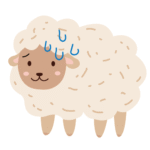
僕もママのイライラが怖かったよ~
意外だったプレスクールでの様子
このような息子なので外でも迷惑を掛けていると思いきや、当時通っていた英語のプレスクールでは『特に問題ない』と評価されていました。
それは、外ではきちんと人並みにできるということではありません。
息子の特性が目立ちにくい状況だったためです。
例えば、ランチボックスには食べれるものだけ持参していたので偏食は問題にならず。
集団で一緒のことをするよりも個々が好きなことに没頭するのが良しとする教育方針だったため、息子の特性が顕在化しにくかったのです。
個が優先され、多国籍でフリーダムな生徒の中では、特性が個性として好意的に変換されていました。
「一人で居ることが多いけれど、それが彼だから問題なしよ♪」と担任談。
普段はお大仏様スマイルを浮かべ、他害や多動などの目立つ行為がない息子は、こだわり行動があってもクラスには馴染んでいたようでした。
絶望した発達支援センターでの相談
こだわりや偏食が深刻化していた2歳後半。
「他の子と違い過ぎない⁉」と悩みが深刻化してきたため、地域の「発達支援センター」へ予約を取ることにしました。
しかし、予約日は最短で3か月後
元々混んでいる上に、コロナ禍の影響でさらに予約が取りづらい状況でした。
それでも、待ちに待った相談日には「何かしらの希望が見えるかもしれない」と期待を持って臨みましたが、返答は以下のようなものでした↓
- それくらいの年齢の子にはよくあること
- それだけでは障害と判断できない
- まだ検査できる年齢ではない
- 言葉が話せているのなら大丈夫
- 色々と深刻に考えて心配しすぎ
- 当方は重症度が高い子を優先している
- プレスクールより自宅で育児するべき
- 仕事をやめて子育てだけに専念できるか
私達の困りごとを「よくあること」「心配しすぎ」と軽視する発言だったり、言葉が話せるか=知能だけを問題としていたり、愛情不足を心配され、仕事をやめて自宅育児を推奨してきたり…。
さらには、「障害児だったら療育に通うために仕事より子供優先の生活になりますが?」と、やんわりと脅しのような話まで担当相談員より聞かせられたのです。
自分の育児を全面否定されたような衝撃を受けましたが、長い待機期間を経てようやく来たのです。
ここで引き下がるわけにはいきません。
少しでも進展が欲しかった私は、事前に調べておいた発達検査について「息子の発達の傾向を知りたいのです。新版K式検査は0歳から対象と聞きましたが…受けることは難しいでしょうか?」と尋ねたところ、、、
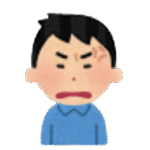
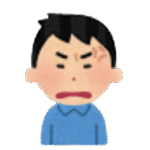
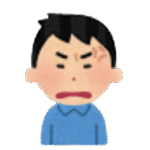
そういうのを決めるのはこっちの仕事ですから!
明らかに不機嫌な態度を返されたのでした。
後で知ったのですが、当時住んでいた自治体の発達支援センターは旧態依然とした古い組織であり、母親に負担を強いるのが当然と思っている支援員が多い、評判がすこぶる悪いセンターでした。
Googleの口コミを見ても分かるのですが、他の自治体の相談支援センターの多くは、もっと親身に相談に乗ってくれると思われます。
ですが、この時の私は実情を何も知らず、「息子くらいの感じだと来ちゃいけなかったんだ」「母親がもっと頑張らなきゃいけないんだ」と思い込んでしまうことになります。
まとめ


特性が強く現れておらず楽だった0歳児育児とは違い、2歳以降は息子が起きている間は常に特性に振り回されて、いつもイライラしていました。
朝はトイレに行く行かないで大喚き、着る服の素材やデザインにイヤイヤ、毎食の偏食で悩み、気分転換で出かければ次々に見かけた「はたらく車」のトミカを要求して道路上で喚き動けなくなってしまう。
ようやく着いた公園でも、まともに遊べず、迷惑行為で謝る日々。
そして、帰宅すればまたトイレや偏食でグズグズや癇癪。流水音に恐怖心がある息子を気遣って、トイレに行くタイミングも自由でない生活…。
ほっと一息つけるはずの家でも、息子のこだわりの無限ループに「ア”ーーー!」と奇声を上げたくなる瞬間が数多くあり、心も生活も乱されていました。
育児は大変で当たり前。だけれど…
特性による「こだわり」に阻害されて、子どもが本来持っているはずの成長が遂げられず、「こだわり」ばかりが目立ってきたこの時期は、辛いというよりは『虚しい…』という表現が相応しかったと思います。
手も愛情も掛けているはずなのに、何も返ってこない虚しさ…
例えば、偏食に関して、日々工夫している食事が完璧に食べらなくたって残す日があったって、それでもいいのです。
半年、一年の長い目で見た時に、「あの時は食べられなかったのに今は一口チャレンジできたね」。そんな風に少しでも進歩を期待できれば、母は頑張れるのです。
でも、進歩するどころか、食べられていたものがダメになり、体重や身長も思うように伸びず、どんどんと後退していくように見えるわが子。
子どもの成長こそ親の喜びでありご褒美なのに、増えるのは困った「こだわり」ばかり…
ワーママ&ワンオペで、夫の理解も得られず、頼れる親族も近くになく、保健センターや発達支援センターでの相談は「様子見」が続き、おまけにコロナ禍だったことが『孤育て』に拍車をかけ、私達親子を苦しめていました。
こだわりが増えた2歳、そしてさらに混迷する3歳へと続きます。