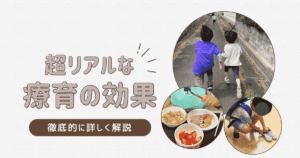羊ママ
羊ママ「うちの子、ほかの子と何か違う…」そんな漠然とした不安を抱えているママ・パパは少なくありません。
私自身、息子が1歳を過ぎた頃から”違和感”を感じる部分が増え始め、育児書が全く通用しない子育てに不安とストレスでどうにかなりそうそうでした。
しかし、健診では「発達は正常」「様子見」と言われ続け、支援に繋がるまでに時間がかかったのです。
この記事では、自閉症スペクトラム症との診断に至るまでの道のりを共有しております。



我が子の発達に違和感を感じている親御さんの参考になれば幸いです。
自閉症スペクトラム症とは


自閉スペクトラム症(ASD)は発達障害の一種。自閉症、高機能自閉症、アスペルガー症候群などが含まれる障害の総称です。最近の調査では、子どもの20~50人に1人がASDと診断され、男性に多く女性の2~4倍とも報告があります。原因は不明ですが、生まれつきの脳機能の特性によるものと考えられています。
「コミュニケーション障害」と「強いこだわり」が二大特徴
この特徴のため、友達との間にトラブルが発生しやすく、学童期にはいじめや不登校、年齢が進むと引きこもりや自殺や犯罪などの二次障害が起こりやすくなると言われています。
こどもに対する治療の基本は、一人ひとりの特性に合わせた「療育」。様々なプログラムの中で、日常での困りごとへの対処法を身につけ、社会との軋轢を回避することを学び、生きづらさが軽減されることで二次障害を予防。療育開始は早ければ早いほど効果的とも言われています。



しかし、特に知的な遅れがない場合、健診などでは見過ごされがち。
そのため、日々子どもと過ごす親の「気づき」が非常に重要になってきます。
子どもの発達障害に気づいたきっかけ


息子の成長を振り返ると、発達障害の特性は少しずつ、しかし明確に現れておりました。年齢ごとに見られた特徴と、私が感じた違和感をお伝えします。
誕生~1歳(ほのぼの期)
2500g未満と小さく産まれたものの発達はほぼ正常、生後3か月頃からはよく笑い、6か月で喃語もよく聞かれ、8か月にはハイハイが活発、ねんトレもスムーズでよく眠ってくれる赤ちゃんでした。
「何て育てやすい子なのかしら~夜も寝てくれてママも7時間睡眠でお肌ツヤツヤよ~」と本気で思っており、子育てで一番楽だったのは、紛れもなく0歳だったと思います。
ですが、今思えば特性かなと思った遊び方は、8か月頃~つみ木を2・3個積んでは崩れる様子にゲラゲラ大爆笑で繰り返す、トミカのタイヤをひたすら回すなど、しつこいくらい同じ遊びに1~2時間没頭していたこと。
当時は呑気にかわいい~♡と動画を撮っていましたが、今見返すと自閉症スペクトラム症に見られる常同行動(繰り返すことでストレスを緩和する行為)のひとつだったように思い当たります。
1歳~3歳(こだわりの爆発期)
この子は他の子とは”何か違う”と気づいたけれど支援に繋がることができなかった苦しい時期でした。
当時は、英語のプレスクールに通っており二言語の負荷があったため、言葉の発達はやや遅かったものの、健診でひっかかる程でもなく順調に発達していました。
しかし、1歳過ぎから味覚過敏で偏食が始まったり、触覚過敏で特定の服しか着られなかったり、聴覚過敏のため特定の音に泣き叫んでしまったり。
感覚過敏が目立ち始め、道順や序列へのこだわりが激しく、トミカを一台ずつ並べ横に寝そべりながら転がしてタイヤが回る動きを永遠に見つめている息子の姿に、「こ…これは…かの有名な特性スタイルなのでは」と検索魔になったのが2歳頃でした。
3歳代は、特に場面切り替えの苦手さからくる癇癪が激化。次の行動や場所に移るまでに何時間もかかってしまったり泣き叫んでしまったりすることが増え、近所の公園に行くことすら一大イベントになっていました。
さらに、対人関係でも孤立している姿が見られることが増えました。3歳になっても一人遊びしかできず、同じ年の子が皆で遊ぶ集団の外で、ひとりでポツンと遠く離れた部屋の隅っこにいる姿も多く見られました。
同じ3歳でもお世話好きな子たちがあれこれ話しかけたり抱っこしたりしてくれるのに、明らさまに嫌がって手を振りほどく光景に、「どうしてうちの子だけで皆と楽しく遊べないの?こんなことで将来やっていけるの?」と胸が締め付けられる思いでした。



また、発達障害児には偏食が多いと聞きますが、まさに我が子も!食事の時間は本当に本当に地獄でした…
まず席に着くことから癇癪が勃発。席についても手をヒラヒラさせて止まらない(常同行動のひとつ)。3度の食事の度に”何なら食べられるのか…”と白目。小さく生まれた上に偏食で、息子の体重がなかなか増えないことに日々必死でした。
レシピ集を見て献立を研究するのはもちろん、親だって滅多に食べられないブランド牛や天然魚などを特別に買って素材にもこだわり、野菜をお星様や花型にくり抜いて楽しげにするなど、全方位に抜かりなく配慮するも…息子の胃袋には響かず全敗。
「好きな物だけ食べさせればいい」というアドバイスもありましたが、幼少期の栄養不足がさらに発達障害を悪化させたらと考えるとそうも振り切れるわけもなく。いつも笑顔のおおらかなママではいたいけれど、”やっとの思いで4か月で0.5kg増やしたのに、ここで気を抜いたらまた元に戻ってしまう”と鬼気迫る心でテーブルにつく私。毎食が決戦の時でした。
栄養か心の安寧か…毎日がせめぎ合い。
楽勝だった1歳までの子育てとは違い、息子が起きている間は常に彼の特性に振り回されていつもイライラしていました。
トイトレも、聴覚過敏のせいで3年近くかかった難題でした。排泄機能には問題ないのに、トイレの流水音への異常な恐怖心で家以外で排泄できずに、幼稚園ではずっと我慢してしまうため帰り道で大量にお漏らしすること数知れず。
もうすぐ4歳だというのに、人間の基本である「食べること」「出すこと」が全くうまくいっていないことに追い詰められていました。
息子の特性から”自閉症スペクトラム症”であることを疑い始めていました。
このような息子なので外でも迷惑を掛けていると思いきや、英語のプレスクールは、ランチボックスに食べれるものだけ持参していたので偏食は問題にならず、多国籍でフリーダムな外国籍生徒の中にいると息子の特性が顕在化しにくいためか、「一人で居ることが多いけれど、それが彼だから問題なし」と特性が”個性”として変換されてしまったり。
健診や保健センターに相談に行くも”言葉や知能に遅れはないし、その他の発達も正常だから様子見”と判断され、先輩ママに相談しても”男の子だからね~うちも大変だったんだよ~”で終了(涙)



困った特性がこれほどあるのに、これが普通なの!?と納得がいかず。
局所的には特性が満載なのに、全体的な発達が正常範囲であることから問題視されず、何の支援にも繋がれなかったこの時期が最も辛い精神状態にありました。
ですが、進んで我が子を「障害児」に診断されたいと願う親などいません。いつか定型発達児のような成長を遂げてくれる希望も捨てきれず、世間から見て息子が”普通”であるならば、親の私の努力不足なのだと悩む日々。
怒りすぎてしまった日には、涙が残る息子の寝顔を見ながら”ごめんね、ごめんね…”と自責の念で圧し潰されそうになり、「神様…お願いだから私を優しいママでいさせてください」と何度も祈ったのでした。
4歳(転換期)
園や行政からの判断では”普通”とされていた息子ですが、ある日”ボタン恐怖症”という極めて稀な恐怖症であることが判明し、いよいよこれは”普通ではない”と覚悟しました。
“みんなちがってみんないい”という金子みすゞさんの名言がありますが、この時の私にはそうは思えませんでした。
何故なら、普通から大きく逸脱した行動が増えると、実際のところ本人も周りも苦労するからです。
生きづらさから二次障害を起こさないでほしい、できれば自分の能力を発揮して社会で活躍してほしい、そのためにはプロによる早期介入=療育を受けたいと切望し、専門医による診察を受けることを決断したのでした。
併せて、まずは母国語でしっかり思考して社会に合わせた表現をすることが自閉症スペクトラム症には必要だと思いましたので、「今は英語をやってる場合じゃない!」ときっぱりと英語環境から離れて、公立幼稚園へ転園しました。
受診から診断まで


発達障害の診断を受けるまでには様々なステップがあります。私たちの経験が、同じような悩みを持つ親御さんの参考になれば嬉しく思います。
病院の決定
健診などのチェックリスト上で何らかの問題があれば、保健センターから受診を勧められますが、年相応の課題には問題がなかった息子は対象外だったため、行政ルートからのアプローチはできませんでした。
行政によっては、健診のチェックリストをクリアしていても、親御さんの悩みによって個別面談や自治体運営の療育へ誘導してくれる場合があるようでしたが、私の場合は健診で相談しても”様子見”になってしまいました
そのため、内科のかかりつけ医に相談して、県立病院の児童精神科への紹介状を書いてもらい受診するルートを選びました。
偶然に1か月後に空きがありましたが、通常は受診まで3~4か月待つこともあると聞いていました。あまりにも待機期間が長ければ、スピーディーさを優先して自己負担を覚悟して個人病院を探すつもりでしたので、公的病院の予約枠が取れたのは本当にラッキーでした。
ちなみに、公的病院であれば検査も保険適応(こども医療費助成で無料である場合も)ですが、個人病院では検査は自己負担で1.5~4万円とのデータもあり、公的病院で検査できて本当に助かりました。



いずれにせよ発達検査は受けるまでにどの病院でも待ちが長いので、一日でも早く受診予約が必要。思い立ったら吉日です!
受診の実際
県立病院の児童精神科には息子と二人で受診しました。
当日、担当医が息子の様子を観察。その後、私からの困りごとのヒアリングと簡易的なASDのチェックリストの聞き取りがあり…
即、「自閉症だと思うから発達検査しましょう」と一言。
え!?…いや、まだ検査とかしてないんですけど…もう自閉症ってことでほぼ決定ですか?と呆然。
”普通”と言われてどうしていいか分からず絶望していたのに、入室から15分で仮診断されるとは。
ショックというよりも、「ああ、ようやく救われた」「私の母としての違和感は間違っていなかったのだ」という気持ちの方が強く、これから正しい方向へ進めるのだと言う希望が湧いてきたのでした。
検査
新版K式発達検査は、1時間程度と聞いていました(個人差があり)。母子同室で入室し、母親は部屋の後方に待機し、息子は机を挟んで心理士さんと向き合う形で検査がスタートしました。息子の場合は、40分ほどで終了。
詳しい検査内容は口外してはならないとの約束でしたので詳細は割愛しますが、知育教具のようなものを何種類も使って課題をこなしていき、発達指数を割り出す検査になっています。
息子の様子は、椅子に座って課題には取り組むことができるものの、心理士さんの話を遮って自分の話を滔々と始めてしまったり、気になる道具を執拗に触りたがったり、難しい課題は早々に諦めて自分流の問題を作ってしまったり。



結果にも書かれておりましたが、”終始マイペース”な様子でした。
診断
実年齢4歳2か月に対して、発達指数は102(4歳3か月)と、やはりここでも年齢相応。
認知・適応領域と言語・社会領域の二領域間に20程度の開きがあり、得意・不得意にばらつきがあるとの評価。
この検査結果を受けて、医師からの説明では”一般的には各能力に15以上の差があると発達凹凸があると認められ、こだわりの種類や強さから判断すると、診断をするのならやはり自閉症スペクトラム症になる”との話がありました。
診断を受けた時の私は、仮診断の時と同じく安堵と希望に満ちていました。
今までは息子は”普通”とカテゴライズされ、育児書や健常児ママからのアドバイスに首をかしげながらも実践しその度に敗北してきましたが、今は標的となる障害が分かりそれに合わせた対処ができるのです。



しかも、「療育」という心強い支援制度もある。これほど救われた気持ちになったことはありませんでした。
しかし、ここでも”普通”の壁に阻まれ、再度絶望の淵に落とされる”ある言葉”を医師から告げられるのでした。
振り返れば「発達障害かも?」と疑った子どもの3つの姿


自閉症スペクトラム診断を経て、今振り返ると、息子には以下の3つの特徴的な行動が見られていました。



お大仏さまのようなニコニコ顔で一見普通なのですが、随所に「こだわり」の塊が鎮座していました。
- 執拗に同じ動作を繰り返したり、回るタイヤを延々見つめる等の常同行動
通常の子どもも繰り返し遊びを楽しみますが、極端に長時間同じことを繰り返すのは自閉症スペクトラムの特徴の一つかもしれません。 - 感覚過敏(味覚・触覚・聴覚など)が多岐にわたること
特定の食感が受け付けない、特定の服しか着られない、特定の音に過剰に反応するなど、感覚の過敏さは発達障害のサインの可能性があります。 - 次の行動や場所に移れずに泣き叫んで癇癪が止まらないこと
場面切り替えの難しさは、自閉症スペクトラムの典型的な特徴です。予定変更や環境の変化に対して極端な抵抗を示す場合は、脳機能がもたらす特性かもしれません。
そして、「ボタン恐怖症」という極めて珍しい特性が決め手となって受診を決意。



「これは普通ではない」と愕然とし、様子見している場合ではないと息を飲みました。
まとめ


「普通」と「障害」の間で揺れ動き、時に自分の感覚を疑い、時に周囲の意見に惑わされる日々。自閉症スペクトラム症の子を持つ親として、診断に至るまでの道のりは決して平坦ではありませんでした。



しかし、母親としての直感は間違っておりませんでした。
息子が0歳から4歳までの成長を振り返ると、常同行動、感覚過敏、場面切り替えの困難さなど、今思えば明らかな自閉症スペクトラム症の特徴が見られました。
それでも、全体的な発達が正常範囲内だったため、健診や保健センターでは”様子見”と言われ続けたのです。
子どもの発達に違和感を覚えたら、その感覚を大切にしてください。子どもにとって一番の観察者は親です。
適切な診察や検査を受けられずにいれば、特性から生み出される生きづらさが深刻さを増し自立できない大人になってしまう可能性がありますし、大人になれば受けられる支援はどんどん少なくなっていきます。
子育ての最終目標は「自立」と言われています。子どもは誰だって何にでもなれる大きな可能性を秘めているのですから、享受できる支援があるうちに効果的に活用して、社会で活躍する幸せな大人になってほしいと願うばかりです。
診断を受けることは、決して子どもにレッテルを貼ることが目的ではありません。診断は、その子の特性に合った支援の「第一歩」となるのです。



早期発見と支援があれば、障害があっても大きく花開く能力を子どもたちは秘めています
もし「うちの子、何か違う…」と感じているなら、ぜひ専門機関に相談してみてください。
そして、相談窓口は一つとは限らないこともお伝えしたいです。健診などで行政機関から”様子見”と言われても、医療機関へ受診することで道が拓ける場合があります(逆パターンもまた然り)。様子見しているうちに大事な成長の時期が過ぎてしまっても誰も責任は取ってはくれません。時間も戻ることはありません。
もし、最初の相談窓口で実情を理解してもらえない場合でも、相談窓口は複数ある場合が多いので絶対に諦めないで下さい。「親の直感」こそ子どもを救う鍵となるのです。